「生きる」という視点/不断不常・不来不出
西田幾多郎の哲学においては、否定の論理がその根底をなしているのでして、ナーガールジュナ の「八不」を解釈するときにも、参考になると思われるのです。そして前回も、前々回もさらに今回もこの手法で考察します。
前回は「不一不異」の解釈について詳細に考察し、仏教の華厳宗の思想でもあり、西田哲学のキーワードでもある「一即多(多即一)」の意味として解釈しました。今回は「不断不常」と「不来不出」を、西田哲学のキーワード「場所」、「行為的直観」および「絶対矛盾的自己同一」などと関連してさらに進展させた解釈をしていきます。
実は以前にも考察していますが、西田哲学と複雑系の科学とはきわめて相性がよいのです。特に今回考察する「不断不常」と「不来不出」とは、「生きている」証を具体的に表現しているように思われるのですが、これについての西田哲学と複雑系の科学はよく一致するところでもあるのです。
すなわち、仏教、西田哲学および複雑系の科学の比較によって、これらの共通の原点として「生きる」、「生きている」ことの追究という主題が見えてくるのです。
「生きる」ということの意味
前々回の考察の書き出しで、「大局的に見て、自然界できわめて数多くの生物が共存しているということから、生物には、どのような偶然に遭遇したとしても、たとえそれが自己と対立(矛盾)するような事物であっても、それを受け容れ共存できるような構造が備わっていると考えられるのです。このためには、開かれていて、入って来る事物に対してある程度自在に対応できる、動的で柔軟な体系である必要があるのです。」と記しています。
例えば、最もきびしい弱肉強食の世界で考察しますと、無数の強弱の生物が存在している場合、強いものに食べられるマイナスと弱いものを食べるプラスとがあり、大局的に見れば確率的に相殺され、ある程度の変動はあるにしろ存続できるのです。当然強い方に属する生物のほうが優位と思われるのですが、弱い方に属する生物ほど繁殖力が旺盛な傾向にあるので、毎年変動はするものの、通常は絶滅することはないのです。
ちなみに、動物に一方的に食べられる植物といえども、植物は大地の栄養分(無生物)を摂取して繁殖し、かつ動物のふんを養分や種子の分散に利用し繁殖でき、柔軟に対応しているのです。極端な例では、人間においしく食べられることで、人間に栽培されて存続している動物や植物も多いのです。
「生きる」ということは、「地球上に多様な生物が無数に存在(共存)している」ことが大前提であり、その結果として「個々の生物はそれぞれと、そして全体(世界)との相互作用を行っている」ことを意味しています。
数多くの多様な生き物が相互作用して存続するということは、相互に促進したり抑制し合うことの連続で、変化のない平衡状態はあり得ず、「変動はするが、その限界を逸脱しない」、言い換えれば「一方的に増加することもなく、一方的に減少(絶滅)することもない」「不増不減」(般若心経)の状態がかろうじて維持されることなのです。
また前回では、「自然を構成しているものは、太陽の光のめぐみを受けて成り立っていますが、地球上の気流(気象)や山や海や川などの無生物と、これらによって生まれ育まれている無数の生物なのです。これらが一体となって自らのはたらきで作用しているのが自然であり、これらは有機体と考えてよいのでしょう。」と記しています。
相互作用するのは生物どうしのみではなく、生物と無生物の間でも行われるのです。ただし無生物といっても生物が住めない、汚染物質の山積みの状態や無菌室のような状態は自然とは呼ばないのです。すなわち「不垢不浄」(般若心経)の状態でないと生物と一体となって機能しないのです。
生物も無生物も、いつまでも安泰な状態が継続することは許されないことなのです。外界の変動によって、たえず変わり続けなければならないのです。これを複雑系の科学では「平衡から遠く離れた状態」とか「非平衡状態」と呼ぶのですが、仏教では「諸行無常」とか「断ぜられる(断絶する)ことなく、常住であることもない」、「不断不常」という言葉で表現できるのでしょう。
以上「生きる」ということは、「相互作用を行っている」ということであり、そのためには、①世界に開かれていること、すなわち外界と物質・エネルギー・情報などの授受をたえず行っていることであり、これらの変化に対応できる②動的で柔軟な適応性を備え、たとえそれが自己と対立する事物であっても協調して共存できるような、対立関係を補完の関係に変換する智慧を生み出すための③否定(抑制)と肯定(促進)の複合的協調思考を備えていることが必要なのでしょう。
「不断不常」=「変動はするが、その限界を逸脱しない」
「不断不常」は前々回で、「断続(刹那滅)」と解釈し、その例として心臓の鼓動で説明しています。心臓は身体の全ての細胞に血液を供給するための、筋肉による収縮と拡張を繰り返すポンプであり、この鼓動(心拍数)と血液の圧力(血圧)は「生きている」証としてのバロメーターなのです。これらの値は身体の活動状態で変動はするのですが、限界を逸脱すると死を意味するのです。
そして生きている間中、血液によって供給される栄養と酸素によって、身体の全ての細胞は無数の「消滅・再生」の新陳代謝の繰り返しを可能にしているのです。
人間の精神も肉体も、常住(変わらない状態)であったり、断絶した状態であることは死を意味するのです。すなわち「不断不常」は「生きている」ことをストレートに表現しているのです。
「不常」は「無常」であり、「不断不常」は「変動はするが、断絶することはない」と解釈でき、「変動はするが、その限界を逸脱しない」ように制御をするホメオスタシスを意味するのです。
この制御は、現象が下限に近づくとその現象を促進させるように働き、上限に近かずくと抑制するように働くように作用させなくてはならず、正のフィードバックと負のフィードバックの複合的な補完機能を必要とするのです。
自然界もこのような仕組みで成立しており、複雑系でいう非線形性のシステムに相当するものであり、西田哲学でいうと人間の思考に関して、否定と肯定の複合的な視点で反省し自覚を繰り返すことで高いレベルの思考に発展していく「絶対矛盾的自己同一」に対応するものなのでしょう。
「不来不出」=「自己と世界との相互作用」
一方「不来不出」は直訳すると「来ることもなく出ることもない」と部屋の出入り口のドアが閉じられた、閉じた系と解釈できますが、この系は現実の世界ではあまり存在しないのです。
中観派のナーガールジュナの言葉であるからには、両極端に固執することを否定する言葉であって、あえて直訳するならば「一方的に来ることもなく、一方的に出ることもない」と解釈したほうが適切なのでしょう。
それでは「一方的に来ることもなく、一方的に出ることもない」とは何を意味しているのでしょう。これは循環していることです。すなわちループ回路が形成され、出たものは必ず帰って来るし、帰って来たものは必ず出て行くのです。心臓は血液循環系の中枢器官とも呼ばれ、全身にわたってループが形成されたポンプです。「一方的に来ることもなく、一方的に出ることもない」は血液の循環が正常に行われていることを表現しているともとれるのです。
ちなみに、現在の原発事故の最大の障害は、循環すべき冷却水が一方的に流出していることにあるのです。
「不来不出」は前々回では「生きる力(成長・増殖)」とか「機能」と解釈しています。すなわち「入力(来)-生きる力(機能)-出力(出)」のループ回路で表現でき、物質・エネルギー・情報などが流入し、そこで何らかの機能が働き、その結果が出力として流出し、これが世界を回り回って元に帰って来る循環系なのです。
すなわち「不来不出」は、「自己と自己や他者や環境を含んだ世界と相互作用を行っている」と解釈することができます。これを下図(図1)に示します。
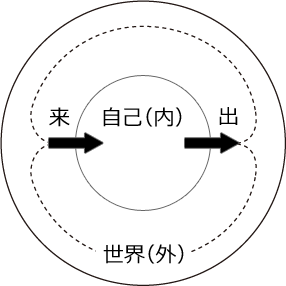
自己と世界との相互作用
仏教思想でも同じと思われますが、西田哲学における「世界」と「自己」との関係は、身体と心臓との関係と同じなのです。世界と自己はそれぞれ独立して、物質・エネルギー・情報をやりとりし相互作用しているのではなく、自己はあくまでも世界の一要素であって、いわば部分と全体とが相互作用しているのです。
心臓も身体の一臓器であり、「来る」は中心に向かって近づく動作を表し、心臓では大静脈を意味します。「出る」は内から外え移る意で大動脈を意味します。自己と世界との相互作用は、心臓と身体との血液循環機能と同じなのです。これは西田のいう「内即外(外即内)」なのでしょう。
自己は如何にあるべきかと三法印
仏教の目標は「己事究明」といわれていますが、「生きる」という視点すなわち「自己が世界と相互作用する」ことから見て、自己は如何にあるべきかを考察します。下表(表1)は、今回の考察をまとめたものです。
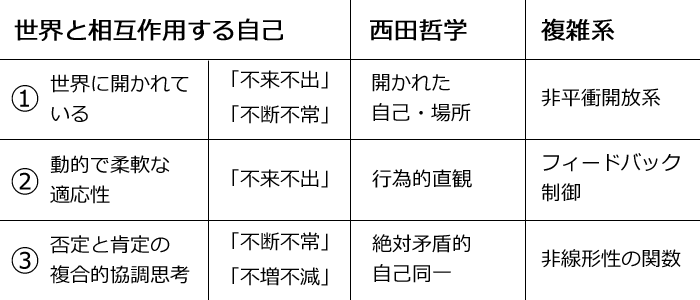
ここで、「生きる」ともいうべき「自己が世界と相互作用する」ことの要件①、②、③は、少し見方を変えれば、前のシリーズの最後の「仏教に関わって五年目の回想」で考察している仏教の三法印①諸行無常、②諸法無我、③涅槃寂静と対応しているように思えるのです。
世界は、自己や他者で構成される人間社会や自然環境ですが、これらは一体となって「生きている」訳で、「不断不常」すなわち断絶の状態でもなく常住でもなく、常に変動しており、これらと相互作用している自己も、常に変化して対応する必要があるのです。これは①諸行無常です。
この変化をするためには融通性が必要であり、事物を「実体」として見て固定化してはいけないのです。②諸法無我は、事物を「実体」視して捉えることを否定しているのです。そして事物を縁起の関係として現象として捉えることを提案しています。これを現代風にいうならば、ハードウェアはそこそこにして、ソフトウェアを重視することなのでしょう。少し表面的な表現になりますが具体的にいうと、人間は地球上での弱肉強食の世界で優位を保つために、強い者の象徴ともいうべき重厚長大な物を装備しようとする指向があるのでしょう。この重厚長大な物を軽薄短小に置き換えるような智慧を生み出し、かつ智慧のすばらしさに目覚め智慧そのものを「生きがい」にするような生き方が、現在必要なのです。これは偶然に遭遇したときに柔軟性・多様性・敏速性の面できわめて有利であるばかりか、ただでさえ狭い国土の自然環境を生物が生きられない「がれきの山」(廃墟)にしないために重要なことなのです。
仏教では、重厚長大な「実体」を否定して、世界と相互作用する自己は、縁起をよりどころとして判断し、智慧と慈悲で実践せよと説いています。
ただしここで重要なことは、縁起は人間にとって完全ではないのです。それは人間の能力では、因や縁を適切に認識できない場合があるからです。また縁起すなわち関わりの世界だからこそ、煩悩や執着が生じると考えることもできるのです。
③涅槃寂静では、因や縁を人間が安易に想定してしまう思い込み、すなわち戯論を滅却せよと説いています。この世の中、必然と偶然が混在しているのですが、人間が考えるほど必然は多くはなく、偶然を無視することはできないのです。涅槃寂静の境地は、否定でしか表現できない世界といわれています。すでに考察していますが、一切の固定化する言葉を否定するということは、一切がランダム(無作為)に起こり得るということを意味し、まさに偶然の世界なのです。また「八不」のように対義語がそれぞれ否定されるということは、肯定でもなく否定でもない中立の世界を意味するのです。
この偶然と対応することは、どのような事物も受け容れる協調(共存)思考を育むことなのです。これらに関してはこのシリーズで考察してきた通りです。
以上「生きる」すなわち「自己が世界と相互作用する」ためには表1の①、②、③を智慧と慈悲で実践することになるのですが、これが仏教の三法印と一致することは、まさに仏教は「己事究明」そのものなのです。