「具象でもなく抽象でもない」絵画
これは「アンフォルメル」の名付け親であるミシェル・タピエの「もう一つの芸術」に対応する言葉で、それまでの抽象画が表現してきた構成的・幾何学的なイメージ(「冷たい抽象」)を脱却し、言葉として表現される以前の意識下の心の状態から生み出されるものの表現としての「熱い抽象」とか「叙情的抽象」を意味する絵画のことです。
第二次世界大戦後、戦争という人間の煩悩や執着が引き起こした、この人間不信が未だ冷めきらない時代を背景に、人間がつくりだした形式や様式を否定して、一度白紙に戻そうという思想です。
時代は全く異なりますが、大乗仏教の思想を確立したといわれているナーガールジュナ(龍樹、150~250年頃の南インドのバラモンの出身といわれている)の思想には、「八不」のような否定の論理がその根底にあり、この否定でしか表せないといわれる涅槃寂静の世界によく似ています。
「諸行無常」という大命題が示すように、西欧絵画の歴史も、19世紀末のいわゆる印象主義の時代頃から大きく変遷しはじめるのです。この時代から第二次世界大戦の後の1950年代のアンフォルメルの時代までの美術史の変遷については、現在開催されているブリヂストン美術館での「アンフォルメルとは何か」が参考になるでしょう。
この美術館はブリヂストンの創業者である石橋正二郎の収集した近代美術を展示するために、1952年に東京の京橋で開館されました。この年代はまさにアンフォルメルの時代で、この美術館も日本での「アンフォルメル旋風」に一役買っているはずです。
「主もなく客もない」から始まる抽象絵画
19世紀頃までは、西欧絵画は「具象」そのもので、写実的な描画が主だと思われます。これはまさに主観と客観の分離の状態で、自己から対象(世界)を見るという視点です。遠近法、すなわち対象を目に見えるのと同じような距離感で正確に描写する方法の理論が開発されています。
19世紀末の印象主義の時代になると、写実的な描写を否定した抽象表現の萌芽が始まるのです。まず対象を抽象化して描くという新しい表現方法に発展します。抽象化するということは主観に重点が置かれることを意味し。主観と客観が接近しはじめるのです。印象主義とは、抽象化の焦点を自然の光に着目したもので、従来の写実を継承しながらも光の変化による情景の印象を強調して描くものです。
さらにポスト印象主義のセザンヌの時代になると多視点描画の表現が採用され、さらにピカソによってこの運動が頂点に達するのです。
次に表現主義の時代になると外の世界(対象)の受け手としての印象を描くのではなく、自らが主体となって自己の内的世界を画面上に表現する自己表出の絵画や、対象を自己の中で完全に抽象化した単純な幾何学的でかつ数色の色で構成される抽象絵画が現れます。
上記の印象(impression)の、外から内に対して、表現(expression)は内から外を意味します。この時代は1940年頃で、以上のような描画方式の否定の繰り返しによって徐々に「主客の合一」の方向に向かうのです。
これは、有形の万物を具象として捉えていたものが、抽象化して捉えるようになり、いわゆる「実体」として捉えなくなったと解釈することもできるのです。そして第二次世界大戦後に、このような背景のもとで、「アンフォルメル」が登場するのです。
「仏教から見たアンフォルメル芸術」で考察しているように仏教思想と相性がよいのも、このような理由からなのです。
具象と抽象の途中経過
「ナーガールジュナの「八不」とは、「ただ今生存中」」で考察した手法で「具象でもなく抽象でもない」を解釈すると、対義語である具象と抽象の途中経過(経路)を意味すると考えられます。
ここで具象とは、個々の事物の形体をそなえた具体的な現象で、仏教でいう「色」(形を有し、生成変化する物質的現象)と同じと解釈できます。一方抽象とは、事物や表象をある性質や共通性に着目して、それを抽出することで把握する心的作用です。
「縁起」によって判断をするとは、判断をする具象に関する何らかの事柄に対して、因や縁に関するそれぞれの言葉や命題を抽出することであり、抽象化を意味するのです。ここで縁起を正しく観るためには、覚者の視点で抽象化する必要があるのです。
以前に「色」か「空」かは、凡夫の視点で見るか、覚者の視点で見るかの視点の違いのみであると考察したことがありました。
「具象でもなく抽象でもない」は、具象と抽象との転換の途中経過(経路)を意味し、事物を理解するときの視点に相当するものできわめて重要な意味をもつのです。
芸術とは、いったん「枠」を通してみる世界
前回は「生きる」という視点から、「世界と相互作用する自己」について考察し、仏教の旗印ともいうべき「三法印」との整合性を明らかにしました。
実は、芸術についても、作品を制作する作者にしろ作品を鑑賞する人達にしろいずれも、自己を生かしている世界とは何か、あるいはその世界で生きている自己とは何かを作品に求めることは、一般に通じることなのです。すなわち芸術も、世界やその中にいる自己を究明することに帰するのです。
前々回のさらに一つ前の「ナーガールジュナの「八不」とは、「ただ今生存中」」以来連続して「八不」を考察してきた訳ですが、これは「八不」が私にとってきわめて意味深い存在だったからです。
このヒントを与えて下さったのが、西田の「純粋経験」の哲学について解説されている上田閑照先生であり、もう一人がこれから紹介するアメリア・アレナス先生です。
この人は1956年にベネズエラで生まれ、84~96年の間ニューヨーク近代美術館の教育部の講師として活動された経歴を持ち、98年に日本人のために出版した「なぜ、これがアートなの?」(福のり子訳、(株)淡交社、1998年2月)が好評だったのです。1995年以来たびたび来日して日本でも有名な先生です。この本は、抽象画が発展した近代および現代美術の独特の鑑賞方法を提唱したもので、ここではその記述の一部を断片的に引用させていたき、考察したいと思います。
『作品の意味は作者の責任外の問題である。
・・・
作品は作者の手を離れたときから一人歩きをする。
・・・
作品にとって重要なのは、作者の意図がいかに表現されているかではなく、結果的にどれほど鑑賞者の意図を引き出せるかということなのである。
・・・
「開かれた作品」と呼ぶべきものの出現こそが、近代美術を発展させるきわめて重要な要素となる。』
普通、作品についての評論家の解説書では、作者の制作時の意図や歴史的背景または技術的な特徴などについて記述するのですが、アメリア・アレナス先生のすごいところは、このようなことは二の次でよいとしています。作品の価値は、作品とそれを見る人とのコミュニケーションによって、見る人がそこから何を引き出せるかによる、としているところです。これは見る人がその作品から何を抽象化して把握することができるかという意味なのです。
そして「開かれた作品」というきわめて示唆に富んだ言葉を提示しています。
次に最終章の一部を引用しますと、
『アートの意味とは、作品が「枠」で取り囲んだ、・・・ものにたいする、私たち自身の直観のなかに存在する。
・・・
あらゆる美術作品は「枠」の外に存在する世界を語っている。それは真の経験の不完全な代役でしかない。にもかかわらず、それは私たちがあたり前だと思っている現実のさまざまな局面に対して、思いもよらないような洞察をもたらしてくれる。』
絵画は、伊達(だて)に額縁で飾っているのではないのです。作品とは、作者が世界を見て洞察して切り取った一つの「枠」なのです。世界を切り取った「枠」の中の作品を見ることで、見る人が何を収穫できるかが、その作品の評価が決まるという訳です。
さて私たちは、世界を見るとか、その世界に中にいる自己を見るといっても、簡単ではないのです。
世界という広い範囲の領域での物事を、何らの先入観なしに見る(抽象化する)となると、焦点が絞り得ないのです。そこで、洞察能力の才能を持った人に要点となる領域を「枠」で限定してもらうと、そこから自己にとっての主要な着目点が発見でき、これを基にして自発自展することで、その「枠」の領域を超えて広範囲の世界の物事が見えてくる(抽象化できる)のです。
世界の物事を適切に抽象化することで「目から鱗が落ちる」ような理解をするためには、何を抽出するかでその成否が決まるのです。このヒントを「枠」が与えてくれる可能性があるということなのです。
すでに考察している「八不」は、世界を見るための「枠」なのです。例えば、「不生不滅」は、我々に「生きる」、「生きている」という視点を提示し、「不断不常」は「変動はするが、その限界を逸脱することはない」という視点を提示しているのです。
仏教でいう「覚り」とは、本人(自己)しだいの問題で、先達といえども如何様にもしがたいのですが、唯一できることは禅宗でいう「公案」なのでしょう。この難問が「枠」に相当するのです。
「熱い抽象」
1950年代のアンフォルメル時代になると、それまでの例えばモンドリアンに代表される純粋で幾何学的な冷たい抽象画ではなく、人間の血の通った、いわば「生きる」という視点から紡ぎだされる熱い抽象画へと変遷していきます。
前々回の「「共通」と「多様」の複眼的視点/「不一不異」」で考察していますが、「一即多」の関係すなわち自己相似集合図形で木を描いています。そのときの図で、具象画というのは図2の「多様」そのものであり、また冷たい抽象というのは、図1の「共通」に属する画面そのものです。特にレベル1の基本パターンは完全に抽象化した画像ということになります。
それでは「具象でもなく抽象でもない」もう一つの絵画といわれる熱い抽象とは、どのような画像になるのでしょう。
下図(図1)は、冷たい抽象として例に挙げた前々回の図1の「共通」要素の画像をレベル5まで実行して木の枝をより多く生い繁らせ、その一部を切り取った画像です。
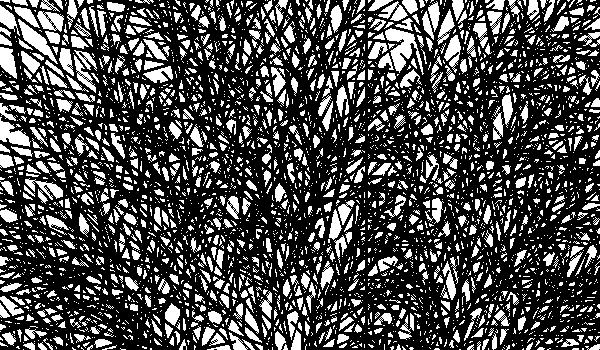
図1.具象と抽象の途中過程(1)
この画像全て直線で描かれているので冷たい感じはぬぐえませんが、ジャクソン・ポロックのオール・オーバースタイルの絵画に似ているとは思いませんか。アメリア・アレナス先生はポロックの絵に関して、『ユングは個々の人々の意識下に、「元型」(人間の精神の内部にある祖先の経験したものの名残りをさす)と呼ばれる普遍的な心象が存在すると唱えた心理学者である。ポロックの「アクション・ペインティング」と呼ばれた制作方法は、自己表現を越えて、その背後にある元型にいたるための方法であった。』と記しています。
木の枝は、その末端に水や栄養を送る働きをするもので、人間の血管に相当します。まさに生い繁った木の枝の交錯は、張り巡らされた生き物の神経や血管の分布や大都市の交通網をイメージさせるものなのです。
下図(図2)は、自然や気象の象徴としての螺旋の美を意識して、木の枝を曲線で抽象表現するために、具象の木として例えに挙げた前々回の図2の一本を、その中心軸の上から約3/5の位置を中心として螺旋に変換したものです。

図2.具象と抽象の途中過程(2)