偶然の定義から導かれる意外な関係
古来から人間社会においては、「これあるとき、かれあり、これ生ずるとき、かれ生ず」で、通常「必然」を基盤として営まれていたわけで、「偶然」という言葉にはあまりなじめないかも知れません。
前から何度も考察していますが、近年「複数の要因が複雑に絡み合った相互関係の世界」には、決定論的カオスが潜み、これが大きな影響を及ぼしていることが明らかになったからこそ、「偶然」がクローズアップされたといえるのでしょう。
今回は偶然の一般的な定義から導かれる意外な関係について考察します。偶然の一般的な定義として、新村 出 著「広辞苑(第六版)」((株)岩波書店)の記述を参照します。これによると偶然とは、
『① 何の因果関係もなく、予期しない出来事が起こるさま。②[哲](ア)原因や理由がわからないこと。人間の認識の不完全さを示す。(イ)歩行者の頭に瓦が落ちてくる場合のように、ある方向に進む因果系列に対して、別の因果系列が交錯して生ずる出来事。(ウ)[論]否定しても自己矛盾を起こさず、その反対を考えることが可能な命題。』とあります。
このように、偶然の定義には、「どうでもいい」とか「やむない」という消極的な意味はないのです。
ここで①や②の(ア)については、このシリーズで今まで考察してきたことです。あえて言うなら、西田幾多郎のいう『純粋経験』の段階に対応するものです。そこで今回は、②の(イ)と(ウ)についてそれぞれ詳細に考察します。
偶然と非線形性の漸化式の実行
偶然の定義②の(イ)について、『ある方向に進む因果系列に対して、別の因果系列が交錯して生ずる出来事』とは、下図(図1)に示すように、二つの線分(ベクトル)1,2の交点に対応します。
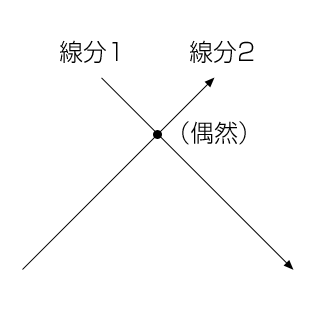
めらめらと燃え上がる因果の方向とそれを吹き消すという因果の方向とは正反対で、肯定と否定の関係にあるのですが、これらが交錯して生ずる出来事(抑制作用)が、偶然という言葉に対応するのです。
因果の方向が両者とも全く同じ方向なら、平行線になるだけで交錯はあり得ないのです。交錯するためには、それぞれの方向が異ならなければならず、互いに抑制し合う成分(ベクトル)が存在することを意味するのです。すなわち、そこに少しでも矛盾が存在しないと偶然は起こらないのです。例えば、全く矛盾のない同じ考えの人がたまたま出会ったとしても、そこからは何も生ぜず、出来事(事件)とは言えないのです。これは偶然とは言わないのでしょう。
西田幾多郎のいう『絶対矛盾的自己同一』だからこそ意味があるのであって、「矛盾のない自己同一」からは何の進展も生ぜず、何の意味もないのです。
さて図1において、しごく当然のことなのですが、いま線分1に着目すると、線分1で起こる偶然(他の線分との交叉)はすべて線分1上のいずれかで起こります。同様に線分2で起こる偶然は線分2のいずれかで起こるのです。これを踏まえた上で、非線形性の関数に話題を移行します。
非線形性の関数については今までに多くの考察をしていますが、特に非線形性の漸化式を実際に計算したときの、各段階ごとの値の変化がどのようになるかの考察は、「仏教思想と自己相似集合」のシリーズの「決定論的カオスを西田哲学から人間の場合に類比する」の題目での「(15)自覚の進展過程をグラフで表現する」の項で詳細に記述しています。
そこでは、非線形性の関数の最も簡単な例として、グラフ上で表現したときに、二本の線分から構成される折れ線の逆V字型の関数について考察しています。この関数は、その形状からテント関数と呼ばれている場合もあります。
このテントの頂点は、二本の線分の交錯する点であり、偶然に二つの事象が出会った場所と解釈することもできます。
ところで、飛躍的な新たな考えを生み出すには、従来全く関係がないと思われていた矛盾する二つの概念が偶然に出会って、そこに共通点が見つかり、新たな考えに発展することになるのですが、このためには偶然の機会を増やすことが、より効果的なのです。
テント形状で表される非線形性の漸化式を実行したときの、ステップ毎の計算結果Xn+1は、テント形状の折れ線上を、延々と重複せずにかつランダムに動き回るのでした。これは、まさに折れ線を構成する二つの線分上で起こる何らかの偶然を延々と引き起こしていると解釈することもできるのです。
この延々と起こる値の変化をに着目して、この変化の特性を図として表現したときに現れるのが「華厳経の風景」の画像なのです。この画像は、決定論的カオス、言い換えると偶然が生み出した何らかの美的な秩序だったのです。
以上偶然の定義②の(イ)において、頭上から瓦や植木鉢が落ちてくる例は、わかりやすいのですが、確率的にきわめてまれな出来事で、これをもって偶然を評価してはならないのです。
われわれは日常きわめて多くの偶然と遭遇しているのです。例えば毎日接している世界中からのニュース(情報)は、我々を新たな事実に目覚めさせ、これによって我々は日々進化していることを忘れてはいけないのです。
そしてこのニュースが、今までの自己の考えと矛盾すればするほど、価値が高いのです。矛盾した事との遭遇が、自己にとつての出来事なのです。
西田幾多郎のいう『絶対矛盾的自己同一』を促進させるのが、偶然(『純粋経験』)の積み重ねであり、これを数学的に表現するなら、非線形性を表す典型的な関数がテント関数であり、このテント関数は偶然の成り立ちを象徴しているかのように思えるのです。
「諸行無常」と「不生不滅」
この「涅槃寂静の世界」を立ち上げるときにけっこう悩んだのは、仏教の大前提が「諸行無常」なのに、「不生不滅」とはこれ如何に、ということです。
「般若心経」の中には、この言葉と並んで、「不増不減」という言葉もあり、増えもしない、減りもしない、すなわち変化しないことではないかということです。
この一見して矛盾しているように思われる、「諸行無常」と、「涅槃寂静」の基となる「不生不滅」の解釈を明確にしておくことは、仏教の三法印のそれぞれとの関連性を考察する上でも重要なことと思われます。
ここで、竹村牧男 著「インド仏教の歴史「覚り」と「空」」((株)講談社、2004年2月)を参考にし、一部引用させていただきます。
ナーガールジョナの中論に関連した「有でもなく無でもなく」という項に大変興味深い記述があります。『かって蝉(せみ)の脱皮を見たことがある。・・・殻を破って透きとおるように白い蝉が出てくる。いくほどもなく、真っ白な身体は茶色に変身するのだった。さて、蝉は蝉から生じたろうか。すでに蝉であるものが、その蝉である自分から蝉になったとはいえないであろう。』
これが、現代人に容易に理解される「不生不滅」の説明ではないかと思われるのです。要するに、変化はするが、蝉は蝉であるということです。
蝉の一生を簡単に記しますと、蝉の雌は樹皮に産卵し、ふ化した幼虫は地中に入って植物の根から養分を吸収し、数年かかって成長し、地面から出て木に登り、殻を破って成虫になります。成虫の期間は1ヶ月程度といわれ、その間鳴いて飛び回りパートナーを探すのです。
前回、前々回で考察したのは「消滅-混沌-新生」という道理についてであり、今回はこの続きで、「新生-生存-消滅」の過程についての考察です。
蝉は生まれ、成長し、増殖などの生存期間を過ごして、やがて死を迎えるのです。このように蝉も生・滅の時期があるのですが、ここで重要なことは、現に存在するものがあると想定して、それが活発に働き・機能しているものであるなら、少しでも持続するのが望ましいのであって、あえて、あらためて生ずることも、滅することも必要ないのです。
すなわち蝉の生存期間においては、成長・増殖などの変化はするのですが、蝉は蝉でなくてはならず、「不生不滅」なのです。人生も同様で、どんなに変化したとしても、自己は自己であって、他者にはならないのです。
この道理については、次の項でさらに詳細に考察します。もちろん「不生不滅」についての従来からの定説としての解釈は存在し、すべての事物は空性であり、縁起で成り立っているので、このようなものを生じるともいえないし、滅するともいえない、ということのようです。
ただし、上記の考察のように、生き物には、時間の長短は別にして、生存期間があるわけで、この期間中は「不生不滅」であって、常に生じるとか、常に滅するという固定化した一方的な考えを避けるために、「不生不滅」という言葉があると解釈したほうが、現代人の私にはすっきりするのです。
事物を「ありのまま」に見るとは、何らかの概念で事物を見ないことです。これは事物を「偶然」として受け入れることなのです。ここで登場するのが、偶然の定義 ②の(ウ)『[論]否定しても自己矛盾を起こさず、その反対を考えることが可能な命題』です。
一方的に(常に)、生じるとか、滅するという固定化してしまう印象を避けたいときの表現として、「生じることもなく滅することもない」という言葉は、生・滅という両端に対して生存期間を意味する中道を表現する言葉として、効果的ではないでしょうか。
生き物の生命を維持する「ホメオスタシス」と「中道」
事物には全てその事物を維持するための何らかの限界があり、これを逸脱するとその事物は破滅(崩壊)することになります。よって事物の進行がその限界に近づいた場合には、それを抑制する必要があるのです。この抑制には、その事物が進行する方向とは逆方向に進行する事物を対応させることが効果的なのです。すなわち対立関係にある、あるいは矛盾の関係にある事物が、共存している必要があるのです。
これがまさに西田のいう『絶対矛盾的自己同一』なのでしょう。そして最初に考察した「非線形性の漸化式の実行」そのものなのです。非線形性の漸化式を実行した結果Xn+1の挙動は、ある点に収束しそうになると抑制力が働いて引き離し、発散しそうになると抑制力が働いて引き込み、延々とその中間の領域を動き回っているのでした。これは仏教でいう一方的に両極端に偏らない中道の思想によく似ていると思いませんか。
ホメオスタシスとは、アメリカの生理学者キャノン(W.B.Cannon,1871~1945)によって命名された、同一の(homeo) 状態(stasis)を意味するギリシャ語からの造語といわれています。生物体の体内諸器官が、外部環境の変化などに応じて、体内環境(体温・血流量・血液成分など)を、ある一定範囲に保っている状態やその機能をいいます。
人間の体温に着目しますと、気温などの外部環境や病気などの内部環境によって、体温は普通36°を中心に変動するのですが、かといってこの基準値を大きく上回って増加したり、大きく下回って減少したら、死を意味するのです。これを防止するための体内の自動調節機能がホメオスタシスなのです。
促進作用と抑制作用、言い換えれば、矛盾すなわち矛(ほこ)と盾(たて)の作用は、自然界で何らかの秩序(バランス)を維持するために必要なのです。
偶然の定義②の(イ)については、偶然とは、肯定的な考えと否定的な考えの接点(交点)とも解釈できます。一方、②の(ウ)の定義では、偶然とは、「そうであること(肯定)も、そうでないこと(否定)もあり得る」という中立(ニュートラル)の表現が可能なのです。
このように偶然の定義②の(イ)と(ウ)とは、中立ということで共通性があります。そして「不生不滅」や「不増不減」などは中道の思想と解釈でき、人間を含む生き物の生命を維持するホメオスタシスの機能とも同じと考えることができるのです。
この道理は、自然界にも人間社会の政治や経済にもいえることで、一方的に増加することは崩壊を意味し、一方的に減少することは絶滅を意味するのです。 要するに「変化(変動)はするが、決してその限界は逸脱しない」ということです。これは竹村先生の記述『変化はするが、蝉は蝉である』と同じと思われます。そしてこれが「中道」や「不生不滅」の本質だと私は考えています。
さて、このホメオスタシスの原理は、以前考察していますが、ノバート・ウィナーの提唱した「サイバネティックス」の実践的な技術であるネガティブ・フィードバックの作用によるものです。
それでは、このホメオスタシスやネガティブ・フィードバックの機能と偶然とはどのような関係にあるのでしょう。
人間が生きていくための必須の機能に、偶然が関与するなどあり得ないと思うかも知れませんが、これは全く逆で、人間が偶然と関与しているからこそ、言い換えれば人間が自分の体温をあらかじめ予測できないからこそ、このような機能が必要なのです。ホメオスタシスやネガティブ・フィードバックの機能は、偶然を前提としたものなのです。